皆様お疲れ様です。
現役看護師のにっと〜です。
突然ですが、皆様体調はいかがでしょうか?
昨今のストレス社会で心に加えて、体にも不調をきたしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
僕自身精神科での経験もあり、心から体など幅広く不調をきたしている方を数多くみてきました。
ストレスから次に生じる可能性が高いのが、怒りの感情かなと思います。
ストレスがかかってくると、怒りを抑えるのが難しくなったりすると思います。
「ついイライラして声を荒げてしまった」、「あとで後悔するのに怒りを抑えられない」――
誰にでも経験がある「怒り」という感情。
看護や介護の現場では、責任の重さ、人手不足や多忙さなどストレスが高まり、怒りの感情が出やすくなることもあります。
そこで役立つのが アンガーマネジメントです。
主に怒りのコントロール法を提唱しており、僕自身もよく実践している内容です。
この記事では、看護師としての経験も交えて、怒りと上手につきあう方法を整理します。
ストレスに関する記事として
元精神科看護師が伝授!ストレス対処法について〜食事、睡眠編〜
も一緒に見てもらえると嬉しいです。
- 「イライラして、自分を抑えられない」
- 「つい感情的になってしまう」
- 「怒りのコントロールの方法を知りたい」
などの方々、是非みてくださいね~

怒りの正体とは?
まずは「怒りとは?」というお話をさせていただきます。
- 怒りは「二次感情」と呼ばれることが多い
- その裏には「不安」「寂しさ」「疲れ」などの一次感情が隠れている
怒りは悪いものではなく、「大切な気持ちを守るためのサイン」と捉えることが大切といえます。
僕には子どもが2人います。
とても可愛くて、目に入れても痛くありません。
ただ、よく怒ってしまうことがあります。
例えば、
まだ歩くこともままならない子どもが机の上を登っていた場合などに怒ってしまうことが多々あります。
怒るたびに「また言ってしまった、、」とやや後悔してしまうこともありますが、これは「子どもが心配」という「一次感情に基づいて、二次感情の怒りに繋がっている」と考えられます。
記事を書いてて、まだまだ未熟やなと反省するばかりです。笑
さて、怒りの正体が少し見えてきたと思いますが、本題の「アンガーマネジメント」について解説します。
アンガーマネジメントの基本
まず、アンガーマネジメントとは、
怒りの感情をコントロールし、衝動的な言動を抑えて適切な問題解決につなげるための心理トレーニングです。
怒らないことを目的とするのではなく、怒る必要のあることは上手に怒れ、怒る必要のないことは怒らなくて済むようになることを目標としています。
一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会 https://www.angermanagement.co.jp/about
アンガーマネジメントの方法は、
- 6秒ルール
- 怒りの温度を測る
- 怒りの背景を知る
などがあります。
具体的にみていきます。
6秒ルール
- 怒りのピークは6秒
- 6秒間、深呼吸や数を数えることで衝動的な言動を防げる
個人的にも一番実績しやすいのは上記と思います。
怒りを感じた際に、一度間を置き、6秒間深呼吸に意識を向けます。
ピークは超えて、少し落ち着くのを感じれると思います。
怒りの温度を測る
- 「0~10」で怒りの強さを自己評価
- 7以上の怒りは一度クールダウンが必要
- 3以下なら「流す」という選択肢も
怒りの温度って少し難しいかもしれませんが、自分でなんとなく「今は5やな」みたいに評価をつけます。
我慢し難い、7以上の自己評価がつけば、一度場所を変えて、一呼吸つくなどを定着化すれば、コントロールしやすいと感じています。
怒りの背景を知る
- 「自分が大事にしている価値観を守ろうとしている」と気づく
- 怒りの原因を紙に書き出すだけでも冷静になれる
人それぞれの価値観があり、それに触れられたり、侮辱されたりすると怒りを生じます。
例えば、少ししょうもないかもですが、
僕はご飯を残すのが嫌いです。
元々両親からは米粒一つでも残すと怒られていた背景もあると思いますが、自身の価値観として、ご飯が残っているのを見かけると嫌な気持ちになります。
飲食店でバイトしてた時には、よく「残すならこんな頼まんかったらいいやん。」とイライラしていたことをアンガーマネジメントの勉強で思い出しました。
僕自身、「食事を残さない」という価値観を大事にしており、それを周りにも求めてしまうこともあると感じました。
ただ僕の価値観が周りも同じわけがないので、上記のように背景を分析することで、周りの人の価値観にも目を向けられるようになったと思います。
職場や家庭での実践例
僕自身もよく行っている実践例をご紹介します。
看護現場の場合
- イライラしたとき → 「6秒深呼吸」をルール化を徹底
- 怒りの温度が7以上なら、環境を変えて、原因と一時的に距離をとる
- カンファレンスで共有し、スタッフに相談しやすい雰囲気づくり
- 記録など書面にに残し、怒りの原因を客観視する
家庭の場合
- 子育て中の「つい怒鳴ってしまう」
→子どもの安全を確保した上で、一時的に「距離をとる」「その場を離れる」 - パートナーへの不満
→「感情」ではなく「事実」を伝える
などがあがります。
基本難しいことは怒りが生じた際にはできないと思います。
・6秒ルール
・環境をかえる
などが比較的対応しやすいことかなと実感しています。
また、怒りを感情のままぶつけると、相手も怒りが生じます。
怒りを「相手を攻撃する言葉」にしないことが大切と思います。
精神科訪問看護で学んだこと
精神科の現場では「怒り」を抱える方も少なくありません。
- 怒りは「SOSのサイン」であることが多い
- 本人が本当に求めているのは「理解してほしい」という気持ち
- 看護師は「共感」「傾聴」「受容」を意識することで、怒りが和らぐケースが多い
「怒りの背景にある気持ちを汲み取る」ことが、現場での大切な姿勢と思います。
まずはしっかりと相手の方を受け止めてあげ、理解しようとしていることを相手にもわかってもらうことが大事かなと思います。
怒りをためない日常習慣
- 睡眠不足を解消する(怒りやすさと直結)
- 栄養バランスを整える(特に血糖値の急変はイライラの原因)
- 運動習慣を持つ(ストレスホルモンを減らす効果)
- 趣味やリフレッシュを意識する
怒りを「出さないようにする」のではなく、「たまりにくい生活」を目指すのがいいかなと思います。
ストレスの解消などについては、
元精神科看護師が伝授!ストレス対処法について〜食事、睡眠編〜
にも記載しておりますので、そちらもよければみてください。
僕の体験談
- 夜勤での睡眠不足、病棟の多忙さより普段より疲れていたときです。
些細なことでイライラしやすくなっており、ちょっとした言葉にイライラするようになっていました。
そんなときにアンガーマネジメントの存在を知り、本で勉強をしました。
簡単に取り組めそうなのが「6秒ルール」だったので、病棟や日常生活でも意識的に行うようにしました。
実際効果は絶大で、突発的に怒ることはほとんどなくなりました。
また自分の中で0~10での怒りの評価を行い、7以上の場合には、その場を離れたり、一度環境を変えることを徹底するようにすることで、イライラを感じてしんどくなるなどのことは少なくなりました。 - 精神科での経験のことです。
精神科では患者様から時折理不尽なことも言われました。
「俺を閉じ込めてる。誘拐犯や」 や「お前が悪いこと全部の原因や」など看護師が悪い表現もされ、病状の問題もありましたが、時にはイライラしたこともありました。
ただアンガーマネジメントを勉強してから、少し自分自身の捉え方が変わりました。
この怒りも二次感情と把握できたことで、「本当に思っている根本のことはなにやろう?」と考えるようになり、「この人は寂しいんや」、「不安なんや」などの怒りの奥にある「感情」を理解しようとできました。
理解できると、関わり方も変わりました。
傾聴や共感、需要というところができるようになり、その方も精神的に安定、理不尽なことで怒ることは少なくなりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「精神科看護師が解説!アンガーマネジメント〜怒りと上手につきあう方法〜」というテーマでお話させていただきました。
怒りは悪い感情ではなく、自分の大切な気持ちを守ろうとするサインです。
大切なのは、怒りを爆発させるのではなく、上手にコントロールすることだと思います。
- 6秒ルールで衝動を防ぐ
- 怒りの温度を測って対処を変える
- 背景にある気持ちに気づく
- 習慣や生活の工夫で怒りをためにくくする
などの手法を用いて、自分ないし、周りの方々と穏やかな日々を送ってもらえたらなと思います。
是非試してみてくださいね。
では本日もありがとうございました。
お疲れ様でした~
※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
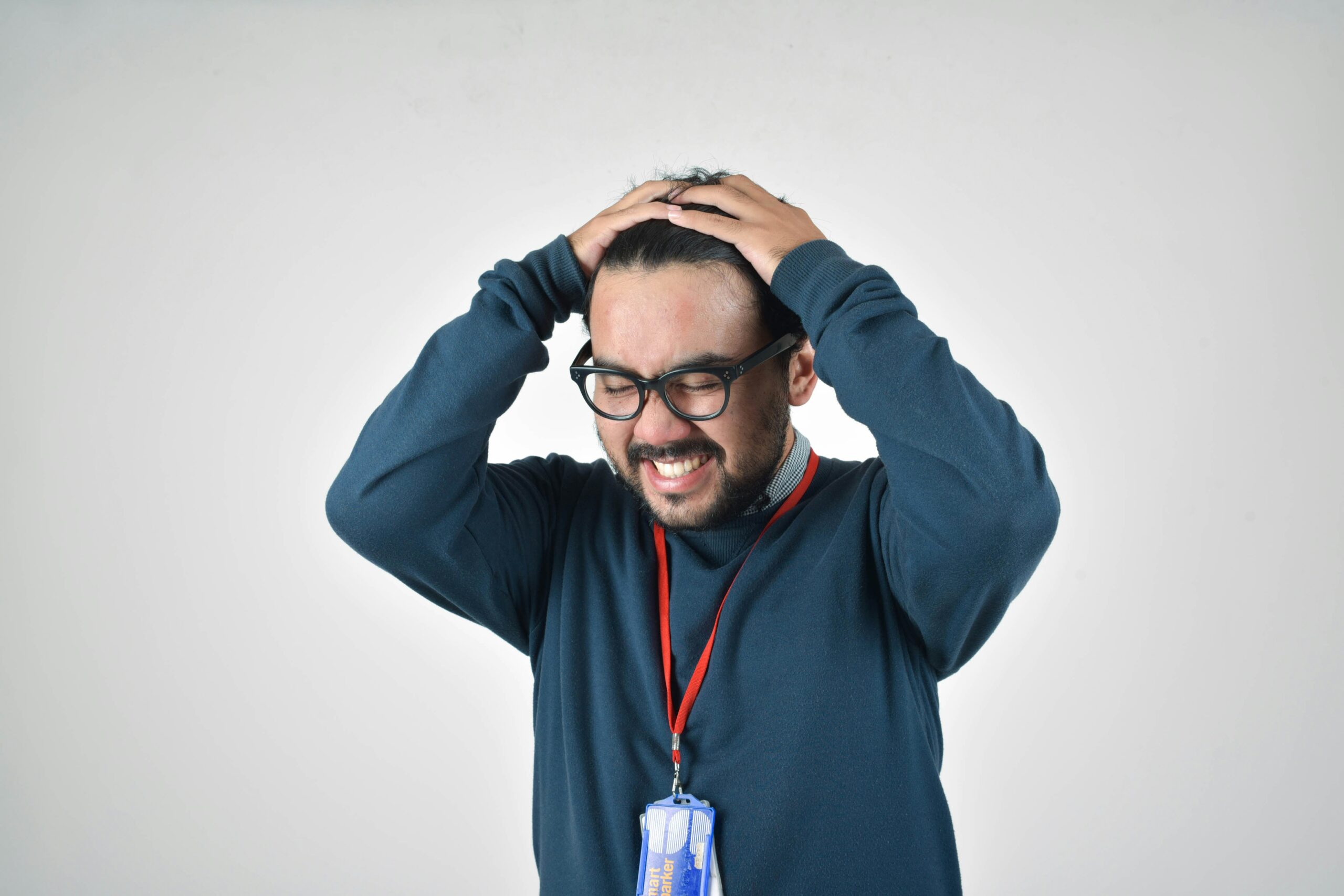
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b7c0d84.2d629d33.4b7c0d85.848da40c/?me_id=1213310&item_id=18048550&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9472%2F9784820719472.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント