はじめに
皆様お疲れ様です。
突然ですが看護学生の皆様、アセスメントについてお悩みではありませんか?
看護学生、看護師なら耳にタコができるほど聞くワードとなっています。
- 「それに対してのアセスメントは?」
- 「ちゃんとアセスメントして!」
- 「記録にアセスメントの内容がないってないから書いてきて」等等。
自分なりにはアセスメントをして、記録にも残しているつもりでも、教員、指導者から見たら「ちゃんと書いてきて」といわれる。
最初はよくわからないなと悩んでいたことをよく覚えています。
今回はそんな皆様のために「看護学生必見!アセスメントってなに?そのコツを解説!」というテーマでお話させていただければと思います。
- 「どうしたらいいのかわからない」
- 「アセスメントで悩まれている」
などの看護学生さん、是非一度みてください。
では本日も最後までみてくださいね~
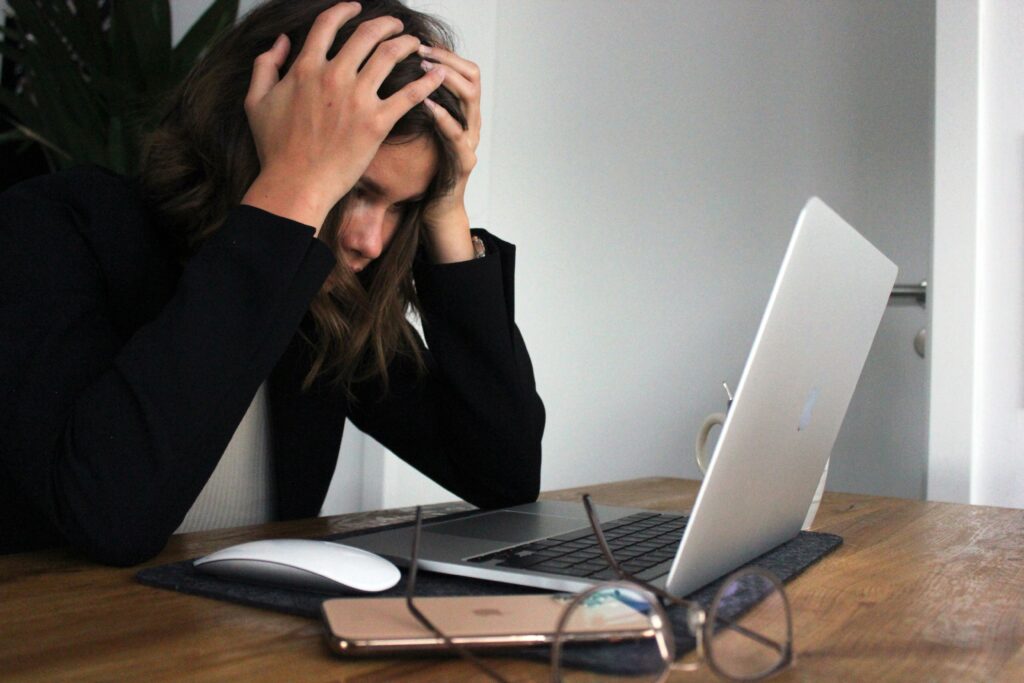
アセスメントって何?
まずアセスメントについて説明します。
アセスメントとは、状態や言動等を「分析する」ことを示します。
看護師の主な役割として、
- 異常の早期発見
- 診療の補助
等があります。
今起こっている症状、状態、言動から、体、心の中で何が起こっているのかを「アセスメント(分析)」し、的確にDrへ報告、相談することが看護師に求められる技術といえます。
アセスメントができていない、していないことは、「卵のないオムライス」みたいなものです。
それくらいアセスメントは重要といえます。
アセスメントをするには? 重要なポイント
アセスメントの具体例を挙げます。
事例
夏の暑い日、独居で過ごされている高齢者がいます。
あまり水分を取っておらず、皮膚が乾燥しています。
昼過ぎにご本人のところを訪ねたところ、意識が朦朧としているのを発見。
右上下肢の脱力が強く、動かすこともままならない。
上記のような状態があったとします。
状況として考えやすいのは「脱水に伴う脳梗塞の可能性」と思いますが、それらを絞り込むためにアセスメントという技術が必要になります。
的確にアセスメントができると、医師へすぐに報告、脳梗塞の可能性があると伝えたうえで、すぐに治療に移れます。
アセスメントがなく、ただ「しんどそう」だけになると、医師が来てから状態把握、検査、問診等になるため、ワンテンポ遅くなります。
その結果重篤な状態、治療にうつれたとしても、後遺症が残る可能性があります。
患者さんの状態はその時その時でも変わりますし、複数の状態が絡み合っている可能性等もあります。
そのため、アセスメントを行うためには、
- その人の普段の状態を知る
- 幅広い知識を持ち、引き出しを多く持つ
等が大事になります。
そのため看護学校ではいろいろな領域の勉強も行いますし、看護実習では普段の様子を知れるように長い時間をかけて関わりができるようになっています。
ただ、知識を持ちアセスメントを行ったとしても、その先にどのような対応をするかも重要なポイントです。
僕自身学生時代に実習の際、
担当患者さんより「脂肪便が出ている」と排便を見て確信しました。
すぐに教員へ「先生。この方に脂肪便が出てます」と報告しました。
「だから?」と返されました。
その時は「なんで?ちゃんと考えてるし、勉強もしてるやん。」となりましたが、今考えると少し恥ずかしくなります。
脂肪便が出ていて、今この方がどのような状態で、かつどのような対応をするべきかまでを考えてアセスメントといえます。
学生時代に上記まで考えて
- じゃあ食事はどのようなものを取っているんだろう。
- 血液データで肝臓とか膵臓が悪くなっている指標とかはないか。
- 嘔気や嘔吐、食事量低下とかはないかな。
等の情報まで確認をとって、今起こっている症状、状態を絞り込み、そのうえで看護ケアに結び付ける、報告する必要がありました。
是非上記内容まで意識して、アセスメントをしてみてください。
またアセスメントの基本としては「フィジカルアセスメント」が重要です。
おすすめの文献を添付しますので、興味があればチェックして下さい。
記録でのコツ
アセスメントをしたとして、学生さんではそれらを文章に残すことで評価につながります。
もちろん看護師になってからも記録に残す必要がありますが、学生さんの場合は、その間に文献を交えて記載する必要があります。
アセスメントの事例を用いて学生さんでの記録の書き方をお伝えします。
あくまでも例のため、すべてをマネする必要はありませんので、ご安心ください。
Aさんは自宅にて独居生活をされている。
高齢者は加齢に伴い、感覚機能が低下し、口渇(のどの渇き)を感じにくくなっている。
また、膀胱の機能低下より頻尿となることから心理的に水分を取らない方も多く存在している。
腎機能の低下や低栄養状態より血管内に水をとどめておくことが困難なこともあり、Aさんは脱水を生じる可能性が高いことが考えられる。
訪室した際に、意識が朦朧とされており、右上下肢の脱力感があった。
上記脱水に伴い、血液の年度は上昇、血栓を誘発し脳梗塞に至ったことが考えられる。
上記のように記載すると、文献での機序の部分を含めたアセスメントとなります。
ちなみに看護記録でのアセスメントや問題点等がそのまま看護計画に反映されていきます。
看護学校で学んでいることはすべてが通ずるもので、一つでは完結しません。
すべてはつながっており、次の段階を考えていくうえで必要な工程と考えてみてくださいね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「看護学生必見!アセスメントってなに?そのコツを解説!」というテーマでお話させていただきました。
アセスメントとは分析することで、看護師には必須のスキルです。
またアセスメントを行うには
- その人の普段の状態を知る
- 幅広い知識を持つ
等が重要です。
記録に起こす際には、しっかりと文献を交えて記載していきましょう。
学生時代にそれらを継続して行っていくことで、次第に自然と頭の中で文献を含めて考えていけるようになると思います。
また、日々の看護記録から看護サマリーなどの書類はすべてはつながっています。
記録だけで終わりではなく、それらが看護計画、しいては看護サマリーなどにもつながっていくため、次の段階を考えるうえでも重要です。
少しでも参考になればうれしいです。
また僕なりにいいと思う勉強方法については
にも記載しておりますので、そちらもご参照くださいね。
看護学生さん向けの記事として
現役看護師が教える!看護計画ってなに?書き方や注意点について伝授!
看護学生必見!国家試験対策 ~勉強が苦手な僕が高得点で合格した勉強方法 3選~
などもありますので興味があれば、また覗いてみてくださいね。
今後も皆様のためになる発信をしていけるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。
では本日もありがとうございました。
お疲れ様でした~
※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b7c0d84.2d629d33.4b7c0d85.848da40c/?me_id=1213310&item_id=19854210&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7816%2F9784896327816.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント