はじめに
皆様お疲れ様です。
現役看護師のにっと~です。
突然ですが、情報共有ってすごく難しくないですか?
僕自身、病院でも勤務していましたが、訪問看護に勤めてからそれを如実に感じています。
まず報連相するところが多すぎると思うんです。
主治医に連絡し、ケアマネジャーに連絡し、次に薬局に連絡し、本人、家族に連絡し、、、
って混乱しません?
ご利用者様の経緯などをステーションの全体にも共有が必要と思うのですが、
文字で伝えるのも難しいし、文書考えてたらすごい時間たってて、記録も残ってるし、結果サービス残業、、
みたいなことありませんか?
僕自身訪問看護にきてから、この辺はすごく戸惑いました。
今回はそんな困ったことや実際にステーションへの共有の対応方法などを検討し、実践してみてのことなどを共有したいなと思います。
是非最後まで見ていってくださいね~

今までの情報共有、課題
僕が努めているステーションは直行直帰で対応している事業所です。
緊急コールを持っているスタッフに関しては、
すぐにご利用者様のところへ走ることができるように各スタッフに1台ずつ社用車があてがわれています。
ご利用者様のところへ家から迎えるのはメリットですが、
ただ直行直帰が故の難しさも存在します。
特に難しいと感じるのは、訪問看護での情報共有の部分です。
直行直帰では他のスタッフと情報共有する場がなく、申し送り等を行うもの難しいです。
また、現在SNSを用いて他スタッフと情報共有をしておりますが、
- 利用者様の数もかなり多い
- 状態変化のたびや、その他共有したいことを連絡する
- 電子カルテでの情報収集にはかなりの時間を要する
等があり、ステーションでもかなりのエラー要因となっております。
まずSNSでの情報共有分がかなり多く、気づけば通知が100件に到達、、等ざらにあります。
必要な情報が埋もれてしまい、重要な指示等を見落とすなどの事象が発生していました。
そのための対応方法として、いろいろ考えて、2つの対応を考案しました。
それを全体に了承を得たうえで実践してみた結果をご紹介できたらと思います。
「ノート(情報共有ツール)」を用いた情報共有
僕たちは「ノート」と呼んでいますが、電子カルテ上のメモみたいなところに
- 「訪問時に対応すべきこと」
- 「主治医指示」
- 「急変時の対応、意向」
- 「駐車スペース」
- 「その他注意点、共有事項」
等をまとめて、訪問時の対応や主治医指示に基づく対応に漏れがないようにしました。
最初、全利用者の「ノート」の更新は骨が折れました。
ノートを作成してからは、
- 訪問の際には各自ノートを確認
- 本日施行する処置や観察点等を把握してから訪問
- 特記での対応が必要な場合にも主治医の指示をノートで確認、対応する
等の対応をするように統一しました。
これにより処置の漏れや必要なケアが漏れることは格段に減りました。
また、スタッフも多く在籍しているステーションのため、しばらく訪問に行っていない人なども急遽訪問に行く必要がある場合もあります。
緊急コールでも同様のことがいえると思います。
- 「どんな人やったっけ?」
- 「どんなケアしてたっけ?」
と記録を確認することはもちろんですが、それに加えてノートを確認することで、より鮮明に行うことがわかるようになりました。
そのためスタッフからは久しぶりに行く方でも安心していくことができるようになったと高評価でした。
ただ、次の課題としては、「誰がそのノートを更新するか」が課題として挙がってきました。
基本新しい処置やケアが増えれば、指示受けをしたスタッフが対応、
ノートの更新をするようにしていますが、どうしても業務が多忙となって忘れる事態が生じています。
どれが最新の指示か、この指示はいきているのか等を把握できないと現場は混乱します。
それらを埋めるために次の対応を考えました。
「リーダー」の配置
情報共有のパイプ役となる「リーダー」を配置することで、かなり業務効率は上がり、
情報共有もスムーズになったと思います。
リーダーの業務としては
- 管理者、役職者の代理、状況判断、スケジュール調整
- 各スタッフから情報を中継、次の勤務者への情報伝達
- 中継した情報から「ノート」を更新、またはフォロー
等を行っています。
情報共有の課題に加えて、元々の課題として、
管理者ないし役職者が休みの日でも連絡がばんばん来る、スタッフの責任意識がやや薄いなどがありました。
リーダー制を導入し、一人ひとりに意識的に全体を見てもらう必要性や調整業務等を行ってもらうことで、
- 管理者、役職者がいなくても、業務バランスを整えられる
- 全体のフォローを行うことで、「ノート」の更新や情報共有の部分でのエラーが減る
- 責任意識、マネジメントの練習となり、次世代を育てることにもつながる
などのメリットがありました。
ただリーダーをしてもらうにあたっては
- その場の状況判断
- 周りを見て対応する視野
- 的確にタスクをこなせるキャパシティ
が必要となるため、一朝一夕にはいきません。
現在おおまかにリーダーができるスタッフは現時点では数名のため、
これが全体に広がればステーション全体の質向上にもつながるだろうなと思っています。
これは今からの課題ですね。
もしうちのステーションではこんなことしてるよ等あれば教えて下さい。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本日は僕自身が「訪問看護ステーションで実際に困った情報共有の部分と、実際に行った対応について」お話させていただきました。
正直答えはないですし、僕自身これが完成形とは全く思っていません。
よりよい方法があるなら導入すべきとも思います。
今回「ノート(情報共有ツール)」と「リーダーの配置」をステーションで導入したため、ご紹介しましたが、あくまでも一例にすぎません。
課題に対して
- どのような対応があるか考える
- 実際にしてみて評価する
- それを再度煮詰める
- 次の対応へ
と考えていくことが重要かなと思います。
また、いい案やこんなことしてるよなどあれば教えてくださいね。
訪問看護での参考資料として、こちらもご覧ください。
また訪問看護での記事として、
看護師勤務で悩まれている方、転職を考えられている方必見!訪問看護のやりがい、メリットについて
訪問看護師が解説!訪問看護と訪問介護の違いをわかりやすく解説
現役看護師が解説!どんな訪問看護ステーションを使うのがいい?徹底解説!
訪問看護への転職を検討している方必見!訪問看護での働き方、業務スケジュールについて解説!
訪問看護への転職を希望する方必見!訪問看護での必須物品4選!
転職を考えられている方必見!訪問看護での看護師勤務のメリット
転職を考えられている方必見!訪問看護ステーションでの看護師勤務のデメリット
訪問看護への転職を考えられている方必見!転職時に気をつけるべきポイントについて解説!
などもありますので、興味があればそちらも見てくださいね。
では本日もありがとうございました。
お疲れ様でした~
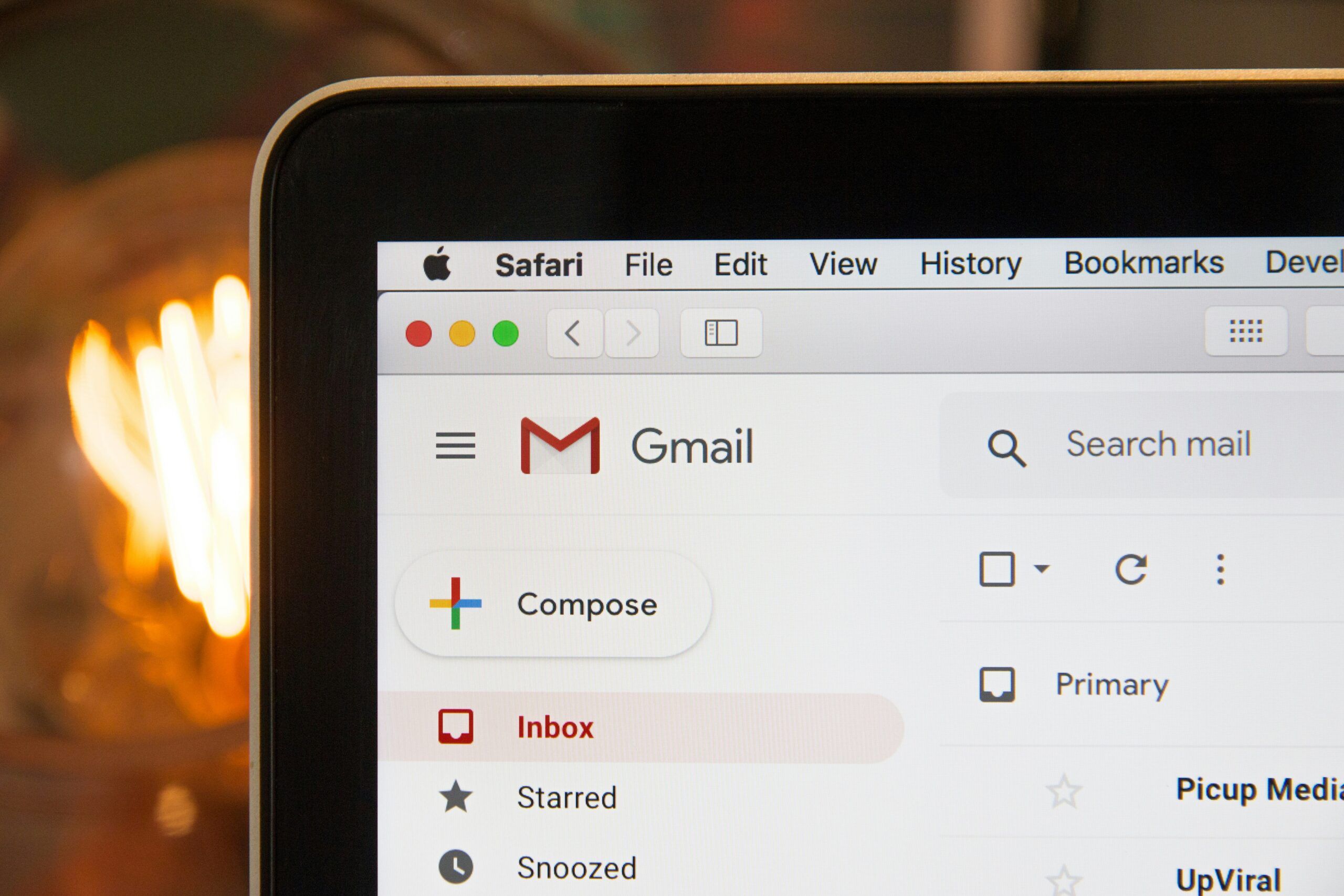


コメント